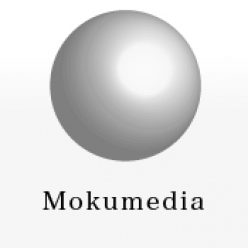木目金
木目金(もくめがね)とは、美しい木目状の模様を織りなした金属、またはその技法の事。江戸時代前期にあたる西暦1651年に生まれた、出羽秋田住正阿弥伝兵衛(Shoami Denbei)本名・鈴木重吉によって発案。
刀装具の職人だった鈴木重吉が、色の異なる金属を幾重にも交互に積み重ね合わせた後、高温で熱して溶かし付けるようにして接合し、現在では鍛造とも言われている方法で金槌で叩いては鍛え、彫っては鍛えるといった事を手間隙惜しまずに何度も繰り返す事によって完成する。

木目金専門ブランドは国内に2社
木目金を扱うブランドは、国内に2社ある。
1つ目は、東京、大阪、名古屋、京都、神戸に直営店を持つ「木目金工房enishi」。
2つ目は、日本全国に数多くの取り扱い店舗があり、伊勢丹新宿店でも取扱いのある「杢目金屋」。
「木目金工房enishi」と「杢目金屋」は、木目金の指輪を取り扱っているという共通点はあるものの、それ以外に関しては全く関係のない別法人であり、制作方法も違うらしい。
木目金の誕生
木目金が誕生する以前、中国には、黒、黄、朱など何層にも重ね合わせた色漆に渦巻文様や唐草文様を掘り下げて模様を出す、「屈輪彫り」という技術があり、その「屈輪彫り」が室町時代に日本に輸入された。これが木目金に結びつく起源なのではないかとする説が有力。
時は江戸時代、その「屈輪彫り」の技術を、展性、塑性(延性)に富む貴金属で応用し、曲げる、捻る、削るなどして木目模様を出すという技術に進化させ「木目金」を発案したのが日本人の出羽秋田住正阿弥伝兵衛(本名・鈴木重吉)。
その出羽秋田住正阿弥伝兵衛(本名・鈴木重吉)が生まれたのは、およそ360年も昔、日本は江戸時代初期(西暦1651年)、慶安という元号だった。
江戸幕府の将軍は徳川家光(とくがわ いえみつ)、徳川 家綱(とくがわ いえつな)。慶安の御触書【けいあんのおふれがき】という法令を江戸幕府が出した時代と言われていた頃もあった。
正阿弥伝兵衛(Shoami Denbei)が作ったとされる最古の木目金は、金・銀・銅・赤銅の4種類の金属を溶かし付けたものを鍛造した小柄が秋田県指定有形文化財として現存している。
鈴木重吉は、江戸で正阿弥の弟子入りをして修業を積んでから秋田へ移住。その後、佐竹藩にお抱え工として仕え、刀装具の名工として名を残している。
木目金の危機
今から130年以上前、1876年に廃刀令が公布された事で、帯刀が禁止。伝承された木目金を知る多くの職人達が廃業に追い込まれる。
江戸時代から続いていた木目金の伝承が一度は途絶えてかけたが、同じ複製を作る事が困難な希少価値。木目金の持つ奥深い魅力に惹かれた人たちの情熱によって、見事に復活。
現在では指輪に使用される事を主に製作者が全世界にまで及んでいる。
世界に伝播。日本の伝統「Mokume Gane」
「MOKUME GANE」は日本よりも海外の方が知名度が高い。
アルファベットのままでGoogleやyoutubeで、Mokume Gane と検索すれば、
その一端を垣間見る事ができる。
杢目金の伝統技術が海外に普及し始めたのが、約30年くらい前。
現在では、スティーブ・ミジェット氏、ジェームス・ビニオン氏などの活躍によって、
世界中に知れ渡るまでに広く普及していった。

江戸時代の木目金と、現在の木目金の違いについて
木目金が完成された江戸時代では、金、銀、銅、赤銅(金3%、銅97%など)、四分一(銀25%、銅75%など)といった貴金属で構成され、大名などが持つ「刀装具」に使われていた。
現在では、プラチナ(pt900)、そしてK18ゴールド(75%純金)のホワイトゴールド、グリーンゴールド、イエローゴールド、オレンジゴールド、ピンクゴールド、レッドゴールド、シルバーなどの色とりどりの色金で、
結婚指輪や婚約指輪としてオーダーされる事が多くなった。
手作り指輪について
木目金は職人が手作りした指輪であるが、最近は自作の「手作り指輪」も人気がある。
名古屋に結婚指輪を手作りできる工房があります。
結婚指輪手作り.com 名古屋工房
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5丁目8−16 1F
0120-487-999
https://www.結婚指輪手作り.com/nagoya.html